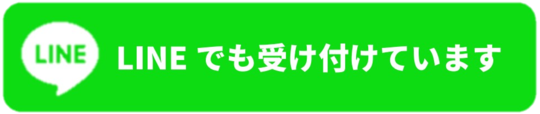全身の筋肉
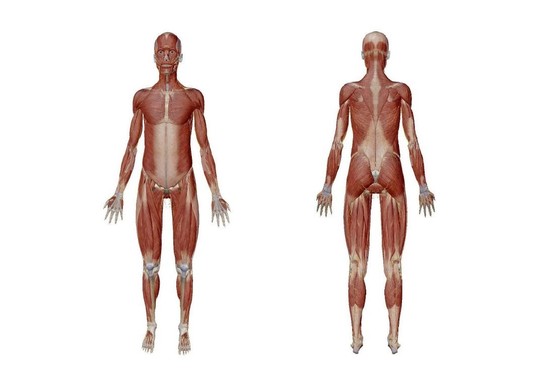
筋肉は関節をまたぎ骨から骨に付きます。
筋肉を収縮させることで体を動かしたり、呼吸をしたりします。
熱を発生させたり、血液を送るポンプとしての作用もあります。
人の体には大小600個以上の筋肉があると言われおり、体重の50%を占めます。
筋肉の主要成分は水で75%を占めています。タンパク質で20%を占めています。
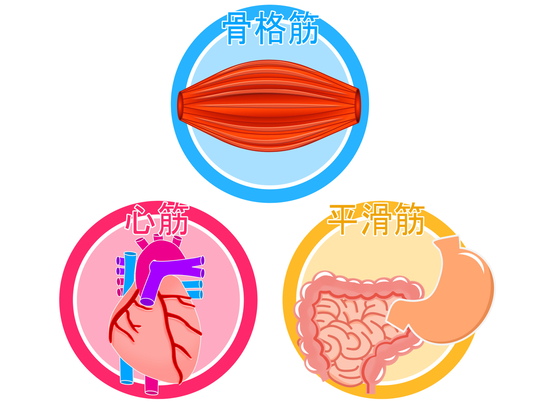
筋肉には
骨格筋(こっかくきん)
心筋(しんきん)
平滑筋(へいかつきん)
という3つの筋肉があります。
骨格筋
「大胸筋」や「上腕二頭筋」などといった身体を動かす筋肉です。
一般的に「筋肉」と言えば骨格筋を指します。
これは自分の意志で動かすことの出来る「随意筋(ずいいきん)」になります。
心筋
心臓の筋肉です。
これは自分の意志で動かすことの出来ない「不随意筋(ふずいいきん)」です。
血液を全身に送るポンプとして働きます。
平滑筋
内臓の筋肉です。
これも自分の意志で動かすことの出来ない「不随意筋」です。
腸では蠕動運動を行い食べ物を運びます。
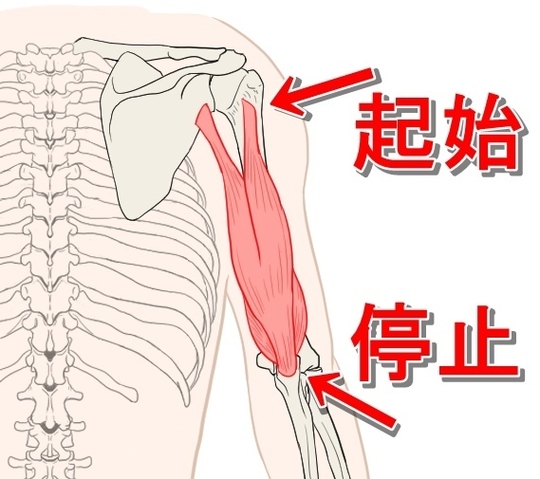
基本的に筋肉は骨に付きますが、筋肉が付く場所を「起始(きし)」「停止(ていし)」と呼びます。
起始は、筋肉(体)を動かした際に、動かないもしくは動きの少ない端のことです。
停止は、大きく動く端のことです。
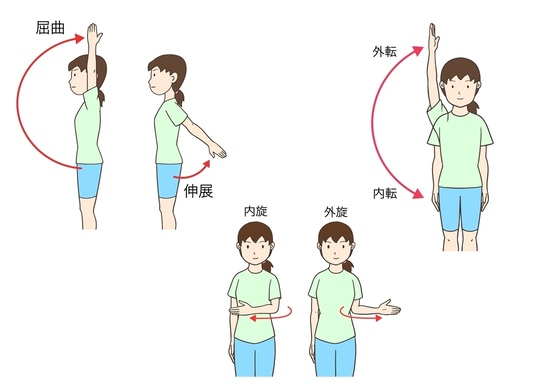
屈曲と伸展
関節を曲げたり伸ばしたりする動作です。例)肘や膝を曲げる(屈曲)、肘や膝を伸ばす(伸展)
内転と外転
体の中心に向かう動作を内転、遠ざける動作を外転といいます。例)腕を横から上げる(外転)、その腕を横から下ろす(内転)
内旋と外旋
腕(上腕骨)や足(大腿骨)などの長い骨を長軸上に回転させる動作。例)上腕の外捻り(外旋)、上腕の内捻り(内旋)
※前腕(肘から手首にかけて)は「回内(かいない)」「回外(かいがい)」といいます。
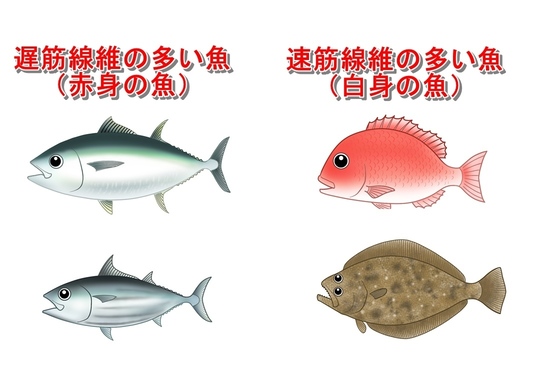
筋肉は速筋線維(そっきんせんい)と遅筋繊維(ちきんせんい)に分けることも出ます。その中間の線維もあります。
速筋線維は早い運動に適していますが、持久力がありません。
100メートル走のような瞬発的な動きで働きます。
鯛や平目のような魚は長い距離を泳ぐことはなく、瞬発的な動きで餌を捕食します。
遅筋線維はその逆です。マラソンのような持久走に向いた筋肉です。
魚に例えると赤身の魚です。マグロやカツオのように回遊魚は長い距離を泳ぐことが出来ます。
中間線維はその中間の役割です。
お問合せ・ご予約はこちら